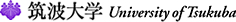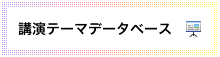社会貢献プロジェクト
令和7年度社会貢献プロジェクト
科学振興
地域と共に育てる宇宙技術プロジェクト教室
| 所属・職名・氏名 | システム情報系 准教授 山本 亨輔 |
|
|---|---|---|
| 概要 |
『地域と共に育てる宇宙技術プロジェクト教室』は、筑波大学が地域の子どもたちと共に宇宙技術を探求し、未来の科学者や技術者の育成を目指す取り組みです。この取り組みでは、大学の専門知識と資源を活用し、実践的な学びの機会を提供します。具体的には、本学学生が、実際にロケット競技会への参加や起業によって得た知識・体験を演習形式で参加者に提供し、宇宙技術の基礎から応用まで『共に学ぶ場』を創出していきます。昨年度から継続・発展し、学内や地域の宇宙関連団体と連携し、地域の宇宙技術文化振興に貢献します。 |
|
先端研究を生かした地域社会貢献型理科教育啓発活動
| 所属・職名・氏名 | 数理物質系 准教授 後藤 博正 |
|
|---|---|---|
| 概要 |
電子工作(ラジオ工作や静電気センサーの製作)、金色と虹色に光る液晶製作、リン光ゲルの作成、遠隔伝送実験、静電気の実験、ムシメガネタイプ偏光板の作成など化学と物理の基礎実験およびデモンストレーション実験を通し、茨城県内の小中高生への理科系啓蒙活動を行う。インターネットによる配信や、液晶セットの配布などを行い、工夫しながら理科教育啓蒙活動を行う。 |
|
バイオeカフェ(筑波大学生命環境サイエンスカフェ)
| 所属・職名・氏名 | 生命環境系 准教授 小野 道之 生命環境学群 生物資源学類 (学生) 生方 寿明 |
|
|---|---|---|
| 概要 |
バイオeカフェはバイオテクノロジーを含む先端科学技術に対する国民的理解の促進を目指すサイエンスカフェ。世話人教員と学生スタッフが協力して企画・運営を行い、学内の教室で18:30から20:00に年間10回を開催する。テーマは生命環境学を中心として、医学や心理学、社会学までも含む。最近、つくば市の広報へ案内を掲載したところ、地元の一般市民の参加が増えた。今年度はオンラインも充実させて社会貢献度をより高めたい。 |
|
加速度センサを用いた地域密着型電子回路教室
| 所属・職名・氏名 | 理工学群 工学システム学類 (学生) 田端 侑心 |
|
|---|---|---|
| 概要 |
地域の小・中学生や高校生に向けた電子回路教室を開催し、現在必要性が叫ばれている情報系・工学系人材の将来的増加と地域への貢献を企図する。教室では筑波大学宇宙技術プロジェクト(STEP)においてロケットに用いられているような実践的な回路を利用して物体の運動を観測して分析を子ども達が行う手助けをする。 |
|
国際
サッカーボールでつなげるTSUKUBA コミュニティ
| 所属・職名・氏名 | ヒューマンエンパワーメント推進局 係長 北條 英次 |
|
|---|---|---|
| 概要 |
週末に大学のサッカー場を開放し、地域住民と在留外国人が気軽に集いサッカーを楽しむ場を提供する。このプログラムはシンプルに、年齢・国籍・性別を問わず参加者が自由にプレーできる形式で進行する。特別なスキルやルールを設けず、誰でも参加できる環境を重視し、試合後には自由な交流時間を設け、異文化理解やコミュニケーションを促進する。サッカーを通じて孤立感を軽減し、多様性を尊重する地域コミュニティの形成を目指し、つくば市の共生社会の実現に向けたプロジェクトを目的とする。 |
|
日韓の青少年による探究型国際交流プログラムを活用した交流事業
| 所属・職名・氏名 | 社会・国際学群 社会学類 (学生) 寳積 應公 |
|
|---|---|---|
| 概要 |
この事業の目的は、日韓の文化を深く理解し、双方の文化に柔軟に対応できるグローバル人材の育成です。異なる背景を持つ人々が出会い、共に学び合う過程において、参加者は国際交流の主体となり、プログラムを通じて異文化対応力を身につけることが期待されます。さらに、日韓両国を舞台に、自身とは異なる価値観や考え方を理解・受容することで、異文化への理解を深め、柔軟な思考力と行動力を養います。これにより、参加者がグローバル社会で活躍できる人材として成長することを目指しています。 |
|
⽂化・地域活性化
地域活性化策とその自立的な運営を支援するロゲイニングの活用とその実践
-大学生と地域の交流から生まれる魅力の発見と発信,賑わいの創出,マップづくりとまち歩き-
| 所属・職名・氏名 | 芸術系 教授 藤田 直子 |
|
|---|---|---|
| 概要 |
日本各地で地域コミュニティの衰退とその振興策が模索されている中,私達は数年に渡りつくば市周辺地域の活性化を地域とともに実施してきた.住民らと共にロゲイニングを通じた「魅力の発見・発信」「イベント」「賑わい」「交流拠点」「まち歩き・マップ」を実現し,交流人口の増加や定住人口の増加への貢献を目指す.本年度は特に海外での活動展開を目標とし,地域活性化策とその自立的な運営の支援策を構築する. |
|
つくさか 食農体験活動支援プロジェクト
| 所属・職名・氏名 | 附属坂戸高等学校 副校長 深澤 孝之 |
|
|---|---|---|
| 概要 |
本プロジェクトは、本校の長年にわたる農業教育活動の実績を原資に、子どもたちや学校教育現場の諸課題解決を目的として、地域の小中学校や諸団体などを対象に、農業や食に関する様々な体験活動の支援を行うものである。学校菜園への指導助言、本校農場での体験学習、食育機会としての給食食材提供などを計画している。実施にあたっては、支援を必要とする子どもたちへの活動を特に重視し、国の「農福連携等推進ビジョン」も視野に、本校生徒との協働学習による、より効果的でインクルーシブな教育機会の創出に努める。 |
|
博学連携による地域文化財の再生と利活用―土浦市における重要遺跡の調査とパブリック・アーケオロジーの展開―
| 所属・職名・氏名 | 人文社会系 教授 滝沢 誠 |
|
|---|---|---|
| 概要 |
地域の文化財は地域固有の歴史や文化を理解する上で欠かすことのできない存在である。近年の文化財保護法改正(2019 年)では文化財の活用がとくに重要視され、文化財の観光利用に向けた動きが全国で進んでいるが、観光利用は活用の一側面にすぎず、とくに地域の文化財は身近な歴史や文化を学ぶ場としての重要な存在意義があることを忘れてはならない。こうした問題意識のもと、本プロジェクトでは土浦市教育委員会と連携しながら市内の重要遺跡を調査し、その成果を市民に還元するためのパブリック・アーケオロジーを推進する。 |
|
視覚障害教育の歴史を広める展示会の実施
| 所属・職名・氏名 | 附属視覚特別支援学校 教諭 村山 彩 |
|
|---|---|---|
| 概要 |
明治期の日本語点字翻案の確立をはじめとして、日本の盲教育を支えてきた本校の歴史を紐解き、地域に向けて視覚障害教育史展示会や学習会等を開催する。視覚障害のある生徒が地域に発信する企画は、附属学校群ミッションにあげられている「多様性を尊重しインクルーシブな社会を実現する人材の育成」の一端を担い、地域交流は「民間企業等とのパートナーシップを推進し、未来を共に作り出す」ことにつながる。これらを通じて、「インクルーシブでグローバルな社会を実現するための教育をデザインする」というスローガン達成に寄与する。 |
|
夏休みアート・マルシェ2025の実施によるウェルビーイングの実現
| 所属・職名・氏名 | 芸術系 教授 吉田 奈穂子 |
|
|---|---|---|
| 概要 |
つくば市は子育て世代の流入により人口増加率が全国の市区部で1位となった。その子育て世代が最も望んでいることは「子連れで出かけられる場づくり」である。そこで、本活動は幼児から高校生までの子どもたちを対象としたアートイベント「夏休みアート・マルシェ2025」を本学芸術系教員や学生、卒業生、つくば文化振興財団、つくば市、その他地域企業とが協力して運営・実施し、研究機関としての大学と社会をつなげることを目指す。保護者と子どもが安心して活動に没頭できる場づくりによってアートによるウェルビーイングを実現する。 |
|
文京ラグビースクール活動支援 ~小学生へのラグビー普及活動の一環として~
| 所属・職名・氏名 | 附属高等学校 教諭 山田 研也 |
|
|---|---|---|
| 概要 |
文京区周辺の小中学生を対象に,2013年4月より開校している「文京ラグビースクール」(通称:BRS)の活動を,本学ラグビー部,附属高校ラグビー部およびそのOB会により支援する。東京都内,特に山手線内はグラウンド確保が難しく,2010年までラグビースクールは存在しなかった。文京区内に広大な敷地を有する附属学校のグラウンド,および日本選手権準優勝の実績を誇る本学ラグビー部の人材を有効に活用することにより,この地区におけるラグビーの普及に貢献することを目的とする。 |
|
コミュニティと共創する水文化を中心とした流域プラットフォーム
| 所属・職名・氏名 | 芸術系 助教 菅野 圭祐 |
|
|---|---|---|
| 概要 |
気候変動に伴う水災害が深刻化する中、流域マネジメントにおけるコミュニティの参画が重視され、住民に身近な「水文化」の価値が再認識されている。しかし、流域という広大な生態地域に分布する多様な水文化の体系的な理解や相互連携には十分に至っていない。本プロジェクトでは、流域全体の水文化を体系的に捉え、水文化同士のネットワークをコミュニティと共創する活動を通して、関係主体間のシナジーを生み出すプラットフォームを生成する。具体的には、水文化をみつける・つなげる・ひろめる、という三つの活動を継続的に実践する。 |
|
地方の子ども支援における教育・福祉・医療の領域横断的専門性の交流プログラム
| 所属・職名・氏名 | 人文社会系 准教授 森 直人 |
|
|---|---|---|
| 概要 |
本プロジェクトは福井県嶺北地方を拠点に、多様なニーズを抱えた子どもたちの支援にかかわる教育・福祉・医療の各領域で蓄積・展開されている専門知・実践知のあいだの交流と対話の場を常設し、その継続的な運営をつうじて当該地方における子ども支援の多職種連携・協働の基盤構築にむけた足がかりとする。申請者が編者として刊行した全2巻シリーズ『公教育の再編と子どもの福祉』を題材に、領域の異なる子ども支援の専門家・実践者が集い議論を交わすなかで、相互不信の払拭と支援のための領域横断的な専門性の「共通言語」化とを図る。 |
|
ほうきをつくろう2025
―つくば市内で生産される稲藁を用いた「つくば式ほうき」の教材作成及び実践―
| 所属・職名・氏名 | 芸術専門学群 (学生) 矢作 百花 |
|
|---|---|---|
| 概要 |
ほうきをつくろうは「ローカルデザイン演習(春学期)/チャレンジ学外演習(秋学期)」という授業の中で、「つくば式ほうき」の作り方を学び、日本各地でワークショップ(WS)を開催する活動である。授業でほうき作りに使用する稲藁は現在長野県で購入しているが、つくば市内で素材調達が可能であると考え、授業外に学生で自主的に活動を行いたいと企画した。最終的には、ほうき作りに必要な素材及び制作方法をまとめた教材を作成し、「つくば式ほうき」を広めることを目指している。 |
|
芸術文化の入り口としての体験型写真展示とワークショップ
| 所属・職名・氏名 | 生命環境学群 生物学類 (学生) 岩田 悠佑 |
|
|---|---|---|
| 概要 |
本企画は、写真をテーマにした展示とワークショップを通じて、芸術文化へのアクセス格差にアプローチすることを目的とする。展示では、現代のデジタルカメラから始まり、カメラ機能を引き算する形で写真とカメラの歴史を辿り、フォトグラムのようなカメラを用いない表現までを紹介する。写真は、誰もが身近に使える手段であり、技術的なハードルが低いことから、子供や若者が創造性を育む初めの一歩として最適である。参加者は体験型ブースやワークショップを通じて、写真を手段とした創造的な学びを得ることができる内容となっている。 |
|
環境
第2回つくば生きもの多様性フェスタの開催
| 所属・職名・氏名 | 生命環境系 教授 上條 隆志 |
|
|---|---|---|
| 概要 |
つくば生きもの多様性フェスタは、つくば市の生物多様性戦略の策定、つくば市の生物多様性センター設立、つくば市、市民、市民団体、企業、大学、研究所など、つくば市の多様な主体による生物多様性保全活動に広く貢献するため、2024年11月に開催された。本プロジェクトは、活動の継続そのものと持続的な活動の基盤形成を目的として、第2回つくば生きもの多様性フェスタを開催する。具体的には、シンポジウム、自然観察会、保全活動を担う市民団体、企業、研究所、本学の研究室によるブース展示、活動主体間の交流促進会を実施する。 |
|
「いもりの里」をモデル拠点とした谷津田・里山の復元・維持管理ネットワークの継続的発展 2025
| 所属・職名・氏名 | 生命環境系 教授 千葉 親文 |
|
|---|---|---|
| 概要 |
「いもりの里」事業では、典型的なある荒廃した谷津田・里山(取手市)を舞台に、地域住民と行政、学術サイドが協働して農村・都市一体型の維持管理ネットワークの構築に成功し、イモリ(絶滅が心配される水生動物)も棲める上質の自然環境を復元しながら、生命環境教育・農業体験・地域産業振興活動などの総合プログラムを実践している。本事業では、「いもりの里」をモデル拠点として発展的に活用・維持しながら、周辺地域への拡充計画策定や周辺小学校・家庭での科学体験学習を支援する。 |
|
生き物観察会 -大塚地区-
| 所属・職名・氏名 | 附属高等学校 教諭 岡部 玉枝 |
|
|---|---|---|
| 概要 |
近年、環境問題について考えさせられる場面が増えている。東京都心部では、樹木や落ち葉が積もったままの自然豊かな状態がある程度の期間維持されているような場所も少なくなり、子どもたちが自然の中で生き物に触れる機会が減少しているのではないだろうか。さまざまな生き物を図鑑やインターネットで検索するだけでなく、附属高校の構内にいる生き物を実際に観察することで、一人でも多くの子どもたちが、生き物に興味を持ち、今後、生態系の保全やバランスについて深く学ぶことができるようなきっかけとなることを目指している。 |
|
健康・医療・福祉
『つくばキッズメディカルユニバーシティ 2025』 ~少年期の子ども対象の医療現場体験ツアー
| 所属・職名・氏名 | 附属病院 看護師長 長田 真理子 |
||
|---|---|---|---|
| 概要 |
知的好奇心の旺盛な年少期の学童にとって医学・医療の世界は非常に関心度の高い魅力的な分野だが、残念ながらその関心と理解を深める実体験可能な場が本邦ではまだまだ少ない。 |
||
不登校児のための支援活動ココ/カラ基地プロジェクト2.0
| 所属・職名・氏名 | 体育系 准教授 澤江 幸則 |
|
|---|---|---|
| 概要 |
我が国における不登校児問題は看過できない現代的な教育問題であるという認識のもと、不登校児にとって望まれる学びの場のビジョンを達成するためのプロジェクト計画を構造化した。そのなか次年度は不登校児のコンピテンスを育てる方法論の確立を目標に、これまでの実績と研究成果をもとに体育場面を活用し、今年度の取り組みで帰納的に発見した方法論を実践しながら検証することと実践方法を効果的に波及させるために評価を行うことと現在対象としている学びの場と関連する学校への実践を計画している。 |
|
障害のある高校生に対する大学進学準備プログラム
| 所属・職名・氏名 | ヒューマンエンパワーメント推進局 助教 長山 慎太郎 |
||
|---|---|---|---|
| 概要 |
大学進学を希望する障害のある高校生を対象に、オンラインと対面形式で大学進学準備プログラムを1回ずつ実施する。オンラインプログラムは発達障害や精神障害を対象に、対面プログラムは全ての障害種を対象に、模擬授業や障害学生メンターとの交流を通じて進学準備を支援する。新たな取り組みとして、障害のある大学生の体験談の共有時間を拡充し、進学に関するQ&Aリーフレットを作成・配布する。さらに、対面プログラムの一部をオンデマンド動画で配信し、全国の高校生や関係者への情報提供を強化する。 |
||
糖尿病の口腔管理についての情報発信を目的とした教育啓発活動
| 所属・職名・氏名 | 医学医療系 助教 工藤 理恵 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 概要 |
歯周病は、糖尿病の合併症の一つとして重症化予防に向けた対策が喫緊の課題である。しかし認知度は低く、患者への支援は十分とは言い難い。本事業では、筑波大学を拠点として、最新の糖尿病の口腔管理の情報発信のための活動を行う。これまでに歯科衛生士や看護師を対象とした研修会や、口腔管理に関心を持つ医療者をつなげサポートネットワークづくりに取り組んできた。本年は、サポートネットワークで得たアイディアをもとに、医科歯科連携システムの導入を検討中の施設に向けて情報提供を行い、糖尿病の口腔管理支援の普及を目指す。 |
||||
発達障害医療に対する当事者向けパンフレット「発達障害の薬はじめてガイド」
| 所属・職名・氏名 | 人間系 助教 仲田 真理子 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 概要 |
我々は2021年に発達障害の理解促進パンフレット「発達障害の薬はじめてガイド」を発行し、配布活動を続けている。情報格差に対処するために積極的にオンラインでの広報活動を行い、これまでに64,400部の冊子を印刷・配布し、高く評価されてきた。2025年度は昨年度挑戦した恒常設置システムの確立と設置拠点の増設に向けて活動を継続する。同時に、インスタグラムなどのSNSを用いたオンライン広報や、学会への出展などの広報活動にも力を入れ、より多くの人が発達障害に関する情報にアクセスできる体制の確立に努める。 |
||||
防災・震災復興
能登半島地震の被災者と被災地のQOLを高める医療・人類学的支援
| 所属・職名・氏名 | 人文社会系 教授 木村 周平 |
|
|---|---|---|
| 概要 |
2024年に発生した能登半島地震の被災地は過疎・高齢化が進む地域であり、地震そのものに加え、遅れがちな復興プロセスが人々や地域にダメージを与えている。そうした状況を踏まえ、本プロジェクトでは、医療と人類学のコラボで、学生も交えて以下のような支援を行う。(1)高齢の被災者を主な対象に、「認知症カフェ」を開催し、現状に自由に話していただき、それをもとにサポートやケアを行う。(2)その語りを通じて地域や個々の被災者の来歴について理解を深める。(3)地域についての聞き書き集を作成する。 |
|
その他
Polar Vision 〜未来を拓く南極の旅〜
| 所属・職名・氏名 | 附属高校 教諭 小松 俊介 |
|
|---|---|---|
| 概要 |
第64次南極地域観測隊に教員派遣として同行した経験をもとに、南極の魅力についてご紹介します。「そうだ、南極へ行ってみよう!」と思えるようなワクワク感を地域社会の皆さんと共有し、日本から14,000km離れた昭和基地のことを身近に感じてもらえるような企画を展開します。年に3〜4回、南極地域観測隊経験者を招き、交流会を計画します。国立極地研究所をはじめとし、気象庁や国土地理院などの研究者、昭和基地を支える企業の精鋭たち、メディア関係者、医療や料理人まで様々なキャリアをもつ隊員との交流の場を設けます。 |
|